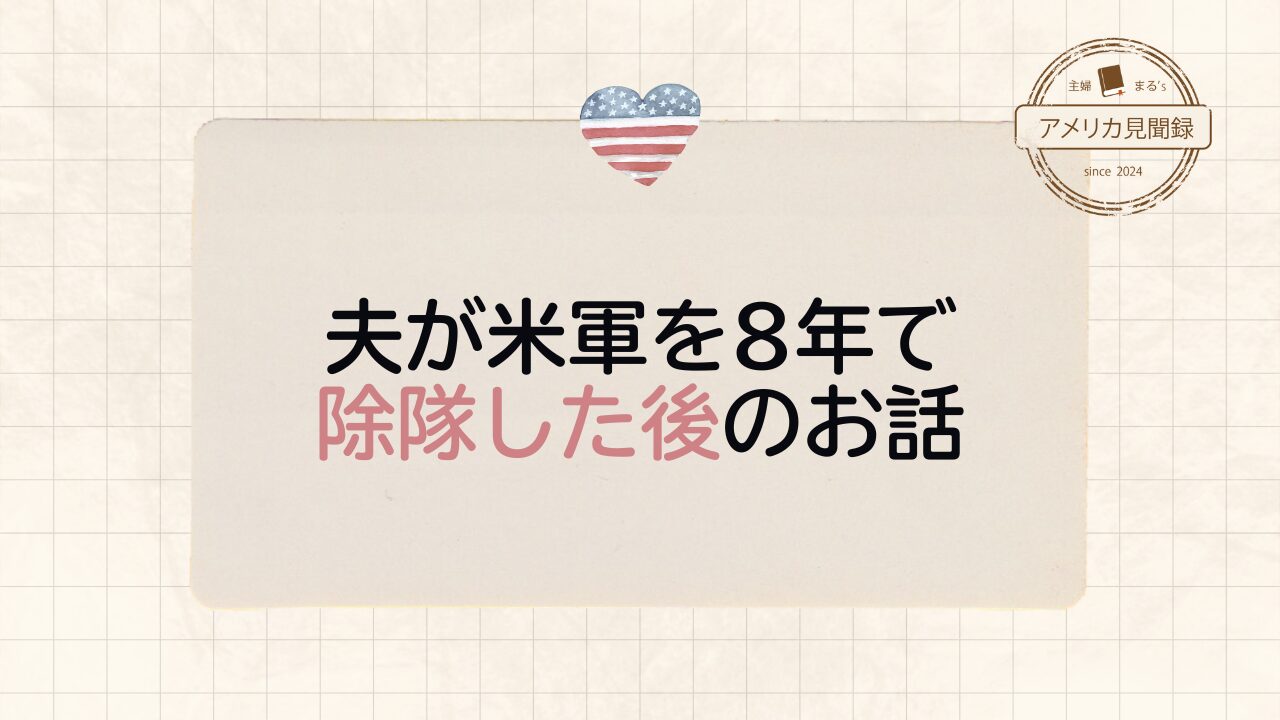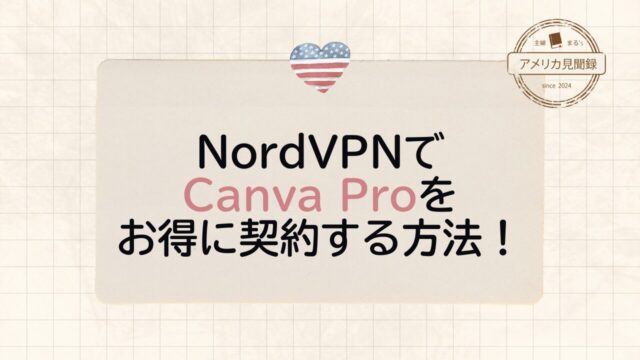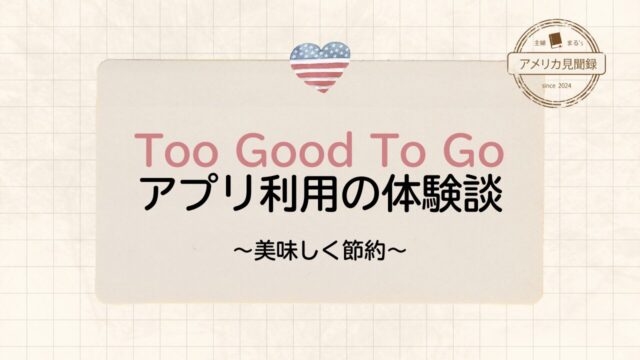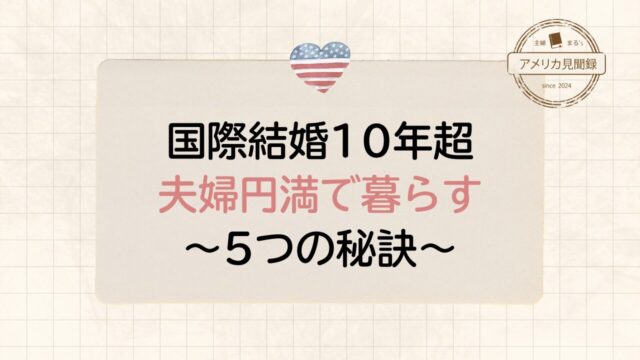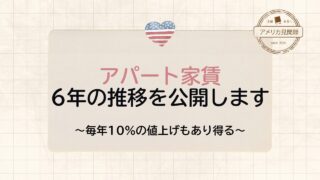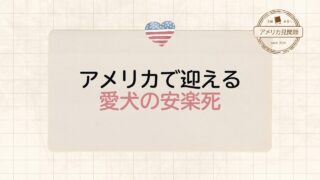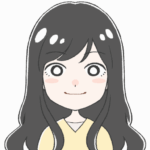こんにちは!元ミリ妻のまるです、まる夫は2016年まで8年間米軍で勤務をしていました。
まる家では夫が米軍を除隊するまでに、たくさんのブログや除隊した人に実際お話を聞くことによって、実際に除隊する準備を進めることができました。
今日は同じく除隊を希望しているカップルや夫婦に向けて参考になる記事になればいいなという思いで書いています!
- 軍をリタイアせずに辞めた国際夫婦のその後の生活が気になっている
- GI Billでの実際の生活模様が気になっている
- 夫や彼氏に米軍を除隊してもらいたく選択肢を模索中である
そんな方々に読んでもらえたら嬉しいです!
除隊までの道のり
我が家も米軍を除隊する前は先の生活が全く想像できずとにかく不安ばかりでした。
ただでさえ(当時E4)生活が苦しいのに、夫が軍隊やめて給料ゼロになるのが恐怖でしかありませんでした。
当時は夫の月々のビール代20ドルを予算として捻出するのが精一杯でした!
今日はそんな生活から、夫とどのようにして米軍除隊から生活を立て直したのか、米軍除隊後の生活についてをお話しします!
除隊して欲しい!という密かな願望
まるがまる夫に出会ったのは、米軍勤務歴3年目の2011年頃です。
結婚前の2年間、短期のTDYや半年のDeploymentを経験し、それなりの覚悟を決めて結婚をしました。
それでもやはり頭によぎるのは「離れ離れにならずに生活ができたらいいなぁ!」という願望でした。
これって米軍勤めの夫を持つ皆さん、一度は経験した事があるんじゃないでしょうか?
除隊という道が向いている人
除隊を希望している人の中で、特に私が個人的に今すぐでも除隊をオススメしたい人は下記のような人たちです。
あくまで除隊したい人の背中を押したいだけであって、キャリアを構築している人に除隊をしましょう!と推しているわけではない事をご理解ください。
- GI Billで大学卒業をしたい(むしろ大卒だ!)
- 今現在のactive dutyの仕事がGSでも存在する
- オフィサーではなくEnlistedである
個人的には米軍で20年という期間を働きあげられる人は本当にすごいな!と思うし、それをサポートする家族も本当に尊敬をしています。
けれども我が家にとっては、夫が軍にいる生活はなにかとコスパの悪い人生でした。
引っ越しのたびに買わなきゃいけなかったり、手放さなければいけないものや人間関係が多かったり、家族も離れ離れの期間も長く、これをリタイアまで続けるのは私たち家族としてはハッピーな選択ではないと、まる家では除隊する結論に至りました。
けれども、米軍を除隊するのは勇気がいると思うんですよね。
今まで健康保険、休暇、住居などの手厚い待遇で守られて来て、急に米軍の外の世界に住むと言ってもそれは同じ国の中の出来事であってももはやカルチャーショックに近いのではないのかなと思います。
勤めた期間が無駄にならないGS
まる家が米軍を辞めるにあたって一番心配したのは、米軍で務めた8年という期間(Time served in military)が無駄になってしまう事でした。
あと12年頑張れば、(いや、その12年が長いのよ。)老後にそれなりのお金が毎月入ってくる。
そこにディサビリティーも一緒に請求して、この先安泰!結局最後まで勤め上げるのは、誰しもあの美味しいリタイアメント(給料の半分が生涯もらえる)に漕ぎ着けたいからだと思うんです。
でも逆に、軍に勤めた期間が無駄にならないのであれば、どうでしょう?
それならちょっと話は別かも!という人は少なくない気がします。
Buy Back Time GS Employee
除隊をしてGSの仕事に就けることができれば、多少の手続きと支払いはありますが、今まで軍で働いた年数とGS職員として働いた年数を足して退職後にしっかりとベネフィットをもらえることができるのです!それだったらどうでしょう?
ぜひ気になる方は「Buy Back Time GS Employee 」と調べてみてください。そのうちにまる夫のケースも記事にしたいと思っています。大まかなイメージとしては、ミリタリー時代に得たベースペイ(基本給)の3%を納める必要があります。
https://maruskenbunroku.com/buybacktime/
まる夫は除隊した時点では高校卒業資格しか持っていなかったので、GS職員になるために、27歳の夫はまずは4年制の大学へ通う一大決心をしました。
GI Billを使った生活
米軍に一定期間勤めるともらえるGI Bill。授業料と教科書代、学校に通っている間の家賃が支給される福利厚生です。米軍を辞めても一度得た権利はそのまま使えるのがありがたいです。
このGI Billを使ってどのように大学生活を乗り切ったのかをお話しします。
BAHでやりくりをする
有給を消化した後、2017年1月からは、ついに今まで当たり前のように入って来ていたお給料がなくなりました。
1月からはGI BillでPSUに通うようになったのでBAH(家賃手当)が入ってくるようになりました。
そして学校に関わる一切の請求はカバーされるので心配ありませんした。
支給されるBAHの額は通う学校の郵便番号を元にBAH Calculatorで調べる事ができます。
学校の所在地の郵便番号のE5(配偶者の有無による)相当のBAHが学校に通っている間、ずっと手当としていただく事ができます。
気をつけなければいけないのは、単位を取っていない長期休み中はBAHが出ないので、その分は事前に考慮しておく必要があります。学校に通っていない分、アルバイトをする時間がたくさんできるので、そんなに心配する必要はないと思います。
2024年のオレゴン州ポートランドを例にあげますね!
PSUの郵便番号は97201
- E5の配偶者ありは$2373
- 配偶者なしの場合は$1836です。
婚姻状況によって支給額に大きな違いが出るのが気になるところです。
軍に所属している間に結婚、グリーンカードなどは済ませておいた方が安心だと思います。
学校に行きながらバイト
まる夫はE4で除隊してE5配偶者ありのBAHがもらえたのでラッキーな気がしていました。
まる夫も私もそれぞれ週20時間くらいのアルバイトをして家計足しにしていました!
正直、1つ上のランクの家賃手当がもらえたことによって、除隊後の生活のほうが安定していたかもしれません!変な話ですが、除隊は若いうちにしたほうがお得感がある気がします…。
学校に行きながらGS
ラッキーなことに在学中にGS8の以前と同じ職種で採用がきまりました。
これは控えめにいってもコネとしか言いようがなかったと思います。
以前同じベースで勤務していた人も除隊し、まる夫がいずれGSに就きたいことを知っていて、「You応募しちゃいなよ!」と言われてノリで応募をすることを決めたまる夫です。
除隊後の夫の人生
| 2016年10月 | 軍勤務を終えて有給消化に入る |
| 2017年1月 | PSU編入 GI Bill利用 |
| 2018年10月 | GS8の仕事が決まる |
| 2020年4月 | GS11の仕事が決まる |
| 2020年6月 | PSU卒業 |
| 2021年4月 | GS12へ昇進 |
| 2021年10月 | PSU MBA入学 GI Bill利用 |
| 2023年6月 | PSU MBA 卒業 |
| 2024年5月 | GS12-13の新しいポジションが決まる |
| 続く… |
これらが米軍を辞めてからの大きな出来事です。
米軍に在籍中に幾らかの単位を取っておいたので、2017年に編入したPSUを約2年半で卒業することが出来ました。
GS8までのランクの仕事は大学卒業資格が求められることはあまりありませんが、GS11以上のお仕事は大学卒業が必須というイメージです。
そのため、PSUの卒業が確定するまではハイランクな仕事は応募できませんでした。
話は一転、大学卒業が確定した頃、GS9〜11の仕事に応募したところ軍人時代の職歴も考慮されGS9スタートではなく、GS11(ターゲット12)のオファーをいただく事ができました。
やはり、学歴社会のアメリカ、大卒である重要さを肌で感じたまる夫でした。
米軍に所属していたころTuition Assistanceを利用して大学の単位を取っていたので、Bachelor’s Degreeを得ながらも、GI Billが余っていたのでMBA取得の道に進むこととなりました。
その間もBAHが貰えていました!
最後の1タームだけGI Billが足りなくなり、貯めておいたBAHを授業料に当て無事に学生ローンを組まずに除隊後のBachelor’s DegreeとMaster’s Degreeを取得することができました。
2025年4月、本来はGS12からGS13へ昇進するはずでしたがトランプ政権のHiring Freezeもあり、昇進が無期延期状態です。
続く…(夫の履歴書みたいな感じになってしまいそうなので、この辺までにしておきます。)
私たちは先の見えない恐怖と戦いながらも、除隊という選択肢をして良かったなと思っています。
現役時代にやっておきたい事
現役時代になるべく多くのリサーチをすることによってスムーズな除隊後の生活を迎えられる気がします。
除隊して8年ほどが経ちますが、今考えるとやっておいて良かったことをあげておこうと思います。
貯金する
備えあれば憂いなしです。
除隊をする前に蓄えられるだけ蓄えておきましょう。
懐の余裕は除隊後の生活の心の余裕につながります。
離職金がもらえる条件に当てはまる人も多いでしょう。まる家はSeparation Payとして$18,000を頂き、BAHの出ない時期(学校が長期休暇の時)に備えました。
大学の単位を取得する
米軍在職中に1単位でも多く取っておいた方が不安定な学生生活を続けずにすみます。
米軍在籍中にTuition Assistanceを積極的に利用して大学卒業に一歩でも近い状態にしておきましょう。
持ち物をミニマルにする
これまでオン/オフベースハウジングなどベースが用意してくれたそれなりに大きいお家に住む機会が多かったのではないでしょうか?
自分たちで家賃を払って住むとなるとなるべく出費を抑えたいところですよね。
学校へ通うとなるとそれなりに都市部でアパートに住む必要もあり、家賃は高くなる傾向があります。
そうすると必然的に持ち物はダウンサイズしておく必要が出るでしょう。
ストレスのない引っ越し、新生活を始める事ができると思います、ぜひ荷物を減らしましょう。
今の職業のコネクションをキープする
今の同僚、上司は将来GSの職へ応募するにあたって大切なリファレンスとして必要になってくる可能性があります。
一度除隊を決めると、この先のことで頭がいっぱいになりそうですが、米軍でのお仕事も最後まで精一杯働いてもらいましょう!
まとめ
私たち夫婦が除隊を考えていた2016年頃、リタイア後の話はあるけれども、こういう除隊後のストーリーがまだあまりなかったので、またどこかで誰かの参考になったらと思い記事にしてみました。
これまで手厚く守られていた環境から、GI Billを使って学校に通いながらアルバイトをする生活はなかなか想像がつかず、不安になるかもしれません。
でも事前に準備をしっかりすることによって、除隊後の生活は安定させることができます。
夫の除隊後のタイムラインは1例ですが、高卒資格だけでも除隊後の生活は夫婦力を合わせればどうにかなるものです。
除隊を希望するカップルや夫婦の参考になればと思います!ぜひ頑張って下さいね!
最後まで読んでくださりありがとうございます。